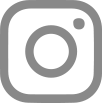niime 百科
Encyclopedia of niime
niime温故知新 茶谷堯典の巻
〈前編〉
“Discovering New Things by Taking Lessons from the Past”
Episode: Mr Takanori Chaya 〈 part 1 〉
〈前編〉
Episode: Mr Takanori Chaya 〈 part 1 〉

2023 . 11 . 05
デザイナー自らが手元に織機を置いて機を織り、想うがままに“実験”を繰り返しながら生地を創作し作品づくりをしてゆく。代表・玉木がそれまでの常識を覆し、分業の垣根を取り払い、播州織産地・西脇で始めた型破りな“モノヅクリ”。
熟慮の末、玉木は確立したその独自のクリエーションの方法論を自分ひとりの内に留めず、広くスタッフを集めてシェアし、産地とこの国のものづくりの将来をも見据え発展・継承させてゆく道を選んだ。
福井にいた頃より旧知の間柄だった玉木本人から、織機の操作とメンテナンスを託され入社した茶谷堯典(たかのり)。意気に感じて未知の分野に飛び込んだ彼だったが、慣れない“超アナログな”機械との付き合いは当初戸惑いの連続だった。
tamaki niimeの発展期にあって、前例のないものづくりのフロンティアで、試行錯誤しつつ自ら道を切り開いて行ったスタッフたちの声を聴くシリーズ「niime温故知新」、今回は内に秘めたtamaki niime愛で会社を支える茶谷の言葉に耳を傾けたい。
—— 茶谷さんがtamaki niimeに入られたきっかけは?
「玉木と酒井…義理の兄になるんですけど、に声をかけてもらって。おそらく力織機を導入したばっかりの時期です。それで、機械のメンテナンス担当として今も伊藤先生という方にお世話になっているんですけど、自社のスタッフも担えるようにということで来てくれへん?というのが始まりです。」
デザイナー玉木が自ら力織機を操って作品づくりへと乗り出し、「589」と呼ばれる最初の小さなShop&Labを構えていた約11年前に茶谷はスタッフとして加わった。現「編みチーム」の山下匡直もほぼ同時期にtamaki niimeの一員となっていた。
—— 全くハタケ違いだったとお聞きしてましたが。
「そうそう。元々僕は足場屋さんやったんで、全然やったことなかったんですけれども、行きます、って速攻で返事しましたね。」
—— なんか面白そうやったと。
「そうそう。即答でしたね。確かその日の晩に返事した記憶があります。そんな時間かけなかったですね。」
—— 入社前はどんな印象でしたか?
「なにかアパレルの世界のことをやっているというのは側で観ててわかってたんですけど、まぁ、“変わってる”なと(笑)。」
—— 二人のやってることが。
「こうゆうビジネスってあるんやなぁ、でも不思議やなぁと。以前から付き合いはあったわけですけど、何をしてるのか謎で。うん、ナゾめいた二人で。それでベルト式の力織機2台入れるからと聞いて。その時も確か観に行ったんですかね、僕。織機自体も見たことなかったんで、なんか面白いなぁと。」
—— 当時新聞報道などで地元でかなりの話題になった記憶があります。デザイナーの玉木さんが自分で機を織り出したと。
「ここに入って色々と機械のことを調べて、他の機屋さんとのお付き合いもするようになるし、そうなるとやっぱり、オカシイことしてんな、と(笑)。そこで初めてなるほどな、って腑に落ちました。あの二人やっぱり、ブッ飛んでるじゃないですか?」
—— そうですよね。。
「そもそもブッ飛んでるけど、要所要所ポイントはしっかりと掴んでいるというか。間違いないな、と。対応速度も含めて、何もかも恐ろしくスピードが速いから、うん。いいなぁ〜って。…それは一回外へ出てみて実感したんですけど。」
—— tamaki niimeを離れていた時期がありましたね。
「一度僕、抜けてみて、あ、そうゆうことか!、って思って。要は一般社会に戻ってみて、こんなにも違うのか、ってところを肌に染みるように感じましたね。」
—— そこはなんというか、tamaki niimeについての核心的なお話ですね。
「居たら分かんないんですよね。それが当たり前になっているから。実際に外に出てみて、一般的な会社に入ってみてやり取りすると…遅いし、と思って。なんや、こんなんなんや…おもんないッ!って思って(笑)。」
tamaki niimeに8年近く在籍し、“niime流”の常識に縛られない事業のあり方とスピーディでスリリングな展開に応えることが日々常態化していた茶谷にとっては、そこを離れてみた時に、他所での業務の“当たり前さ”が、物足りなく感じられたということなのだろう。
「そこで確信しましたホントに。世の中の動きって遅いッ!、って。」
—— これじゃアカン、と。
「こんなんじゃヤバイやろという(笑)。結果的にこうして戻って来れて…さらに感謝の念を持って戻って来れてる感じなんですよね。」
決して多弁ではないものの、独特の感性の鋭さと真っ直ぐで一途な性格が、訥々と語る茶谷のその言葉の端々から漂ってくる。
「いつだったか、ミーティングで玉木と言い合いみたいになって。その日に辞めたんですけど。もう勢いで。上に噛みついてしまった以上、もう引くに引けんなと。次の日には後悔しましたけどね。…ただのアホですよ。一緒に住んでた(義母の)初子さんにめっちゃ怒られましたもん。」
—— そうでしたか…。
「空白の3年間、思えばあっという間でした。」
力織機を導入し自らそれを操って製作に打ち込み、代表作となるショールを産み出し、大きな反響を得始めた後、tamaki niimeとしての方向性を熟考した玉木は、己れ一人の作家性を打ち出すのではなく、播州織の伝統と職人技術の継承をも視野に入れ、様々なスタッフを集めて事業の拡大へと舵を切った。そのタイミングで声を掛けられたのが茶谷だった。
「当時は玉木が自ら力織機で織ってたわけですけど、他にもやるべきことが多いから、そこの手を止めるわけにはいかないし。あれって付きっきりになるから。それも含んでのことだったと思うんですけど、力織機触って、って頼まれて。機械モノは好きではあったんですけど、織機ってまた違うじゃないですか。それも超アナログな機械で。最初はそれですね、わからないまま…」
日々壁にぶつかれば、現在もメンテナンスの教えを乞い先生と呼ぶ地元の機料店(繊維機械の専門店)の伊藤義忠さんに相談するか、玉木に直接訊くかの二択だったという茶谷。玉木には他の取り組みに専念してもらうべく毎日のように伊藤さんを呼んで観に来てもらっていたそうだ。
レピア織機の部品は今も手に入れられる状況だが、ヴィンテージと呼べそうなベルト式力織機となると、交換が必要となった古い部品が入手できない場合、機料店と鐵工所に依頼し特注で鋳物の部品を製作してもらうのだという。
「あれも相当古いから、一ヶ所だけ部品を新しくすると、バグるんですよ。面白いもんで、いい感じに機械みんながヘタってないと。」
—— 不具合が起こるというか…なるほど、ひとつだけ新品の部品が入った時に。
「おかしくなるんですよ。そこがホントに難しいところであり、面白いところなんですよね。」
—— なんか生きものみたいですね。
「新しい部品に替えればそれで良いかというと、そうじゃないんです。機械を触ってゆくうちにそうゆうことがわかるようになって来て。」
—— 新しい部品はだんだんと馴染んでくる感じですか?
「だんだん馴染んできます。そこは稼働した時の音で表現するから。ちょっと動きがおかしいなって時には変な音を出してるんですよ、“あの子”って。逆にわかりやすくて良いです。そうなった時にはエグい糸の切れ方とかするんで。早めに気づいてあげないと…」
—— 暴れる、みたいな(笑)?
「そうそうそうそう。」
—— ほんと、生きてるみたいですね。
「ほんとにあのベルト式力織機は超アナログですから。」
—— 2台ともそんな感じですか?
「2台それぞれにクセがあるから。触ってて全然違います。Labに入って向かって左側の子は重たくて扱いづらいというか。入念に準備して動かしてあげんと。右側の子は軽いです。今は僕が織機を担当していた頃よりもだいぶアップグレードしてますね。」
「最初は力織機をよう触れんかったですね。」という茶谷。まずは当初2台あったレピア織機から始めて操作に慣れていった。
「一度試しに動かしてみようとして、まだ玉木が『only one shawl』を織っている途中で触ったら、ガシャーン!!、…と。経糸をバッサリ切っちゃって、織れなくなっちゃって。すっごい怒られて…すごく大事な時期だったんですよ…。」
—— 操作ってやっぱり難しいんですね。。
「クセをつかめば、何となく感覚はわかってきますけどね。ボタン押したら即回るというタイプじゃなくて、補佐して一緒になって動かしてあげんとあかんから、あの子は。特に始動の時とか。人の寝起きが重たいのと同じで。」
—— むちゃ人間的ですね。
「ほんと人間的なんですよ。性格ありますもんね。」
—— そこが準備が要るってところですね。
「その方が、機嫌良く動いてくれるかなと思いながら僕はやってましたね。きれいに掃除して、油差して。ほんとに入念にしようとしたら準備だけで3、40分かかりますから。なんかトラブった時でも、その方が後悔がないし。やることやっておいた上でならしゃあないなってなるけど。後でクヨクヨ原因を考えるのって嫌じゃないですか。」
—— 動かす前にまず掃除と手入れから。
「そうですね。油が溜まってたり、たまにあるんですよ。本来そこの部品に届いてなくちゃいけないオイルホースが途中で切れてたりとか、緩んで抜けてたりとか。亀裂が入って油が漏れてる場合もありますし。」
—— へぇ〜…。
「きれいな状態にしてあげないとホースそのものが見えないじゃないですか。だから掃除しといた方が原因がわかりやすいですね。」
—— ほんと茶谷さんが入社される前の導入最初の頃は、玉木さんしかベルト式力織機は扱えなかったわけですよね。織りたい一心で勉強されたんでしょうけど、それもスゴイことですよね。
「レピア織機じゃなくて始めから力織機触ってたわけですから。僕にはそんな勇気ないなと思いましたもん。」
究極の柔らかさと心地よさをとことん追求するためには、ヴィンテージのベルト式力織機でないとこれ以上の風合いは出ない、その都度人に頼むのではなく自分で織るしかない。そう決意した玉木。無我夢中で織機と遊んでいたと当時を振り返るものの、「only one shawl」を産み出すまでの、古い織機と幾度となく対話を繰り返しながら扱いこなせるようになるまでの苦労も並大抵ではなかったことだろう。
—— ホールガーメント横編み機導入時、山下さんが最初のニット作品づくりで勝手が違って納得できるものが創れず玉木さんからもOKがもらえずに数ヶ月かかって、一斗缶にしゃがんで作業していた記憶しか残ってないと仰ってました。
「そうですね。ペンキの缶ね。しかも寒くてね。昔のLabは無茶苦茶底冷えして…僕もその時いました。お兄ちゃん(酒井)にあったかいダウンとか買ってもらって。僕の方は僕でその隣で織機回してたから。経糸が頻繁に切れた時があって。今となっては大したことない数ですけど、その頃は無茶苦茶手も遅いし、100本くらい切れたらエッ…?って呆然となってたんですよね。でも自分がやらんと誰も助けてくれないし、回らないから。」
—— それは前回の取材で阿江さんも同じようなことを仰ってましたね。ニューヨークへ行った時に、自ら動かないとtamaki niimeは世界に広がって行かないと考えるきっかけになったと。
「阿江さんも大変だったと思いますね。ニューヨークっていう新しい土地で展開していこうというなら、なおさら。…相当なプレッシャーだったと思うんですよ。玉木も厳しいし。言い訳できないし、もうやるしかないから。」
—— 当時、茶谷さんも山下さんも阿江さんも、それぞれのポジションで未知のフィールドに向き合いながら、悪戦苦闘されてたわけですよね。
「やらなしゃあなかった。ほんまにそうなんですよ。やらな前へ進まへんかったから。それを玉木に向かって切れてる糸を結んでください、っておかしいじゃないですか?自分がやるしかない。」
—— 皆さんそれぞれに、替わる人のいない責任を負っていたということですね。
「『洗い』なんかも、『589』の頃はシンクが無くてお風呂で洗ってたから。風呂場に洗濯機が2台あって、なんせ動線が良くなくて靴一回脱いで行かなくちゃならないし、かがむから姿勢がキツイし。お風呂の後に洗いをする場合があって…暑いんですよ(笑)。夏場にウール洗って…でもその状況って経験してないとわからないし…今のLabの設備の充実はありがたいことなんやで、って、ここからスタートしたスタッフにはわからないかもしれないけど、そうゆう時代があったんだよっていうのをね、知っておいてほしいなって思いますね。」
〈続く〉
織機を導入し自社で機を織り「一点モノ作品」の創作を手掛ける、現在に至るtamaki niimeの創成の頃。玉木や酒井とともに茶谷たちスタッフは、新たな独自の“モノヅクリ”の可能性を求め冒険へと乗り出した。
それは各々が意を決して、tamaki niimeにとっての未知の領域の開拓へと向かった時期と言えるだろう。その挑戦を恐れないフロンティア精神は今に息づいている。
シリーズ「niime温故知新 茶谷堯典の巻」。〈後編〉では、玉木と酒井の素顔をよく知る彼が観た二人の人間像、そして義母であった初子さんのこと、溢れるtamaki niimeへの想い…が熱を帯びて語られます。
どうぞ次回をお待ちください。
書き人越川誠司
After thinking deeply, Tamaki didn’t keep her method, which she had created, to herself but shared it with her staff, who gathered and chose the way to develop and inherit for this district and the nation’s future.
Takanori Chaya and Tamaki have known each other since they were in Fukui. At Tamaki’s request, he joined the company to operate the loom and maintain its maintenance. Being impressed with her enthusiasm, though, at first, he had continual difficulty dealing with unfamiliar super analog machinery.
In the series of niime “Discovering New Things by Taking Lessons from the Past”/’niime Learning from old and new’,’ we listen to unprecedented frontiers in manufacturing open to reveal their ways of overcoming difficulties with trial and error at the developing time of ‘tamaki niime’. This time, we hear from Chaya, who supports ‘tamaki niime’ with his passion for the company within.
——What brought you to ‘tamaki niime’?
“Sakai is my brother-in-law. He and Tamaki talked to me when they just got the looms. They had Mr Ito who was, and still is, in charge of taking care of the machine’s maintenance, but they also needed their own staff for maintenance, so they asked me to be the one.”
The designer Tamaki challenged Chaya to work to make products, and Chaya joined their staff 11 years ago when they had a small shop and lab called ‘589’. Masanao Yamashita, who is in the ‘knitting team’ at present, joined ‘tamaki niime’ as one of the staff at about the same time.
——You have worked in a different field, right?
“Yeah, that’s right. I worked as a scaffold assembler and have never been a maintenance worker, but I replied back quickly, “I will do it.”
——You thought it seemed interesting.
“That’s right. I replied back immediately. I remember I did so on the evening of the same day I was asked. I didn’t take time to think.”
——What was your impression before you got into the company?
“I knew they were an apparel company just by looking from the outside. They were…unique. (laugh)”
——What they were doing.
“I was curious that this kind of business existed. I have known Tamaki and Sakai for a long time, but I didn’t know what they were doing. Yeah, those two were mysterious, and then I heard they would have two belt type power looms. I surely remember going to look at them. I have never seen looms, either. I was amused.”
——At that time, it became a hot topic in the local newspaper that Ms Tamaki, a designer, started weaving independently.
“I have learned a lot about looms after getting into here. I came to talk to other people at loom shops and found out Tamaki and Sakai were doing unusual things. (laugh). That’s when I first realized it made sense. Those two are crazy!”
——You are right…
“In the first place, they are crazy, but grasped essential key points. They are surely making no mistakes. Including their response speed, everything is very fast. Yeah, they are so good. I really knew it, after I once quit here and worked at different place.”
——You had a time when you were away from ‘tamaki niime’, right?
“Once I left here, and realized how different it was. In short, working at a regular company, I really felt their differences on my skin.”
——That is the core part of ‘tamaki niime’, right?
“You can’t realize it while you work here because it has become commonplace. If you go outside and look at how regular companies interact with them, you realize how things go slowly. Oh, no! That’s how they are…not exciting. (laugh)”
Working at ‘tamaki niime’ for almost eight years, he got used to the niime way, which is not bound by common sense, responds speedily, and experiences thrilling developments. After he left, he was not satisfied with the ordinary business way of other companies.
“I was really sure that the movement of the world is so slow.”
——You thought it was not good at all.
“I realized it’s terrible. (laugh) I could end up coming back…I feel more than thankful to be back here.”
He doesn’t speak much, but you can feel his unique, keen sense of honesty and unswerving, single-hearted character from his stammering words.
“I wonder when it was, but I had an argument with Tamaki at the meeting and quit my job that day. I did it on impulse. I bit my boss, and couldn’t take it back. I regretted it the next day. I am just stupid. Hatsuko, my mother-in-law, scolded me a lot.”
——Is that so…
“Three blank years, it was over in a flash when I think back. “
Tamaki had looms and wove to create products, such as shawls, representing her work. After getting a big reputation, she pondered her direction for ‘tamaki niime’. She decided not only to gain her authorship but also to keep Banshu-ori tradition and inheritance of craftsmanship; she gathered various staff to take the helm in developing the business. Chaya was the one she called at that time.
“At that time Tamaki wove on her own, but she had so many other things to do, however, she couldn’t stop weaving, because once you start weaving, you had to keep doing it. I think because she wanted me to do it, and asked me to weave with looms.I liked to use the machines, but the looms were very different, because they were very analogous. At first, that was a problem. I really didn’t know about them.”
Every day, whatever problems he faced, he asked Mr Yoshitada Ito, the owner of a local textile machinery speciality store who still helps teach maintenance at present and is called ‘teacher’, or asked Tamaki directly. He wanted Tamaki to concentrate on other work, so he asked Mr Ito to see the machines daily.
You can still get the parts of rapier looms, but when it comes to belt machinery looms, which can be called vintage, if there are no old parts that need to be replaced, you have to ask a textile machinery shop and steel cast factory to make steel parts on a particular order.
“They are very old. If you change one part with a new part, it stops working because it has a bug. To be interesting, they have to be all worn out.”
——I don’t know if it is called malfunction…I see when only one new part gets in.
“It goes wrong. It is a really difficult point and interesting as well.”
——They look like a living creature.
“It doesn’t mean there’s no problem if you change it to a new part. I am beginning to understand as I take care of machines.”
——Are new parts working well with the machines?
“Yes, they do gradually. I can tell with the working sound. When they have problems, they make funny noises, ‘those guys’. Vice versa, it’s easy to understand it. When it has a problem, the thread breaks in a very nasty way. I need to be aware of it in advance.”
——They go wild? (laugh)
“That’s exactly right.”
——It sounds like they are alive.
“Those belt type machinery looms are super analogous.”
——Two of them are like that?
“Each one has their own characteristics. They are totally different when we use them. One on the left when you get in the laboratory, it’s heavy and hard to handle. You have to get ready before using it. The right one is light. They are upgraded now more than when I was in charge of them.”
Mr Chaya also said, “At the beginning, I couldn’t handle the looms well. At first, I started using 2 rapier machines to get used to handling them.”
“One time I tried to use it while Tamaki was weaving ‘only one shawl’, and it made a big noise, ‘crash’! The warp thread was cut completely and it made it unable to weave. I was scolded hard…because it was a very important time…”
——It’s hard to handle machines.
“If you catch their characteristics, you would know how to handle them. It’s not just pushing a button and working. You have to assist it to work together, specially that machine needs to help at starting, just like humans don’t work well when they just wake up.”
——They are just like humans.
“Yes, they really are. They have personalities.”
——That’s how you need to get them prepared.
“I believe in doing so to make them work well in a good mood. I clean well and put oil in, which takes 30 to 40 minutes for preparation. If there’s trouble, I won’t regret it. It can’t be helped if I have done what I had to do. I don’t like to think about the cause of the trouble after it happens.”
——Before moving the machines, clean and care for them.
“Yes, I do. There’s some oil left, which happens sometimes. The oil hose that is supposed to reach some parts is sometimes cut off in the middle, or it’s loosen and falling out. In some cases, the oil leaks from the crack in the hose.”
——Oh, I see.
“If I don’t make the hoses clean, I can’t see them. It’s easier to see the cause of troubles if it’s clean.”
——At the beginning of having looms before Mr Chaya joined the company, Ms Tamaki was the only one to handle the belt machinery looms. She studied with the sole desire to weave it, which is fantastic.
“She tried the looms, not the rapier machines from the beginning. I don’t think I had such courage.”
“To pursue extreme softness and comfort, you can’t get them if you don’t use vintage belt machinery looms. Tamaki couldn’t ask someone whenever she wanted, so she decided to do it alone. Thinking back about that time, she played with the loom in a daze. It was a great challenge to be able to handle the old looms and learn how to weave while talking with them many times until she finally produced ‘only one shawl’.
——When he got whole garment flat knitting machines, Mr Yamashita had a hard time making his first knitting products because they were very different from his past experiences. His pieces couldn’t even get accepted by Ms Tamaki. He said that he only remembers sitting on an 18-litre drum for months.
“Yeah, that was a paint can, and it was freezing. At the old laboratory, it chilled to the core… I was also there at that time. My brother-in-law (Sakai) bought me a warm-down coat. As for me, I was weaving by him. The warp threads broke frequently, which was not too much time now. At that time, I was slow and shocked when 100 threads broke. But there was no one to help me.”
——In the previous interview, Ms Akou said a similar thing. When she went to New York, it was time to realize that if she didn’t work, ‘tamaki niime’ wouldn’t spread to the world.
“I think Ms Akou had a hard time trying to develop at a new place in New York. She must have had a lot of pressure. Tamaki is strict, too. Ms Akou couldn’t make any excuses. She had to do it.”
——At that time, Mr Chaya, Mr Yamashita, and Ms Akou each had different positions and faced unknown problems. They were battling at work.
“We had to do it. That’s the fact. We couldn’t keep moving forward if we didn’t do it. We couldn’t ask Tamaki, “Please tie the broken threads. That’s not the way. I had to do it.”
——Everyone had responsibilities that nobody could replace for you.
“When we had the shop 589, we did ‘wash’ at the bath tub because we didn’t have a sink. There were two washers at the bathing place. The flow line was not very good, so we had to take off our shoes to go to the bathing place, and even bending over made posture difficult. After taking a bath, we did ‘wash’…… so it was very hot. (laugh) We washed wool in summer… you wouldn’t understand such situations without the experience … We are so thankful for the fully equipped laboratory facility now…the staff who started with it may not understand it, but I want them to know there was such a time.”
< continued >
At the beginning of ‘tamaki niime’, Tamaki got the looms, wove at her own company, and created ‘one item products’.
With Ms Tamaki, Mr Sakai, Mr Chaya and other staff, they started on an adventure to seek the possibility of their own new ‘creation’.
That was when each of them decided to explore unknown territory for ‘tamaki niime’. Their brave, challenging frontier spirit lives on today.
In the series niime “Discovering New Things by Taking Lessons from the Past”: episode of Mr Takanori Chaya
Please look forward to the next episode.
Original Japanese text by Seiji Koshikawa.
English translation by Adam & Michiko Whipple.