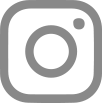niime 百科
Encyclopedia of niime
niime百科 くる年2023
新春“ポンコツ”談義〈後半〉ー ポンコツの極意!
A New Beginning 2023
New year ‘shooting the breeze’ — The Secret of Airheads!
新春“ポンコツ”談義〈後半〉ー ポンコツの極意!

2023 . 01 . 18
〈前回からの続き〉
酒井「だから、昔の『見て盗め』って、スゴいことやと僕は思うんですよ。」
—— ええ。
酒井「今の世の中って、1から10までを教えて〜ってなるけど、僕が17歳で働き出した時には『見て盗め。』って言われてたから。訊いたら怒られたし。当時のその感覚とか、その“距離感”とか。どこまで行っていいのかな〜アカンのかな〜ここまでは良いだろう、とか。」
—— なるほど…。
酒井「自分の目でしっかり見て盗んで、その人の前で体現して、褒められたり評価を得るという。」
—— “体感・体得”ですよね。
酒井「そうですそうです。」
—— そこはアタマで理解しようとしても駄目だと。
酒井「駄目です。」
玉木「うん。」
—— 私のグラフィック・デザイン修行時代なんかもそうでしたけど…師匠のやってることを観て自分の手を動かして身体で覚えてゆくという。
酒井「今のウチのスタッフなんて、下積み期間なくて入社して直ぐにデザインできるでしょう?」
—— そこはありがたいことですよね。
酒井「今、デジタルが発達したせいで、パターン化しやすいんですよね。人間の分類がしやすいんですよ。“ダイバーシティ”とか言われてるけど、でも、昔の方がもっと色んな多様性があったから。」
—— 枠にはめにくい、データに置き換えられない部分があったというか。
酒井「デジタル技術の多様性が逆に人間のありかたを簡素化させたというかね。」
—— 情報に絡め取られるのでは貧しいというか…手で触れてやってみることの大切さを痛感しますね。
ヴァーチャル世界がリアルを脅かしてゆくような時代。画面のクリックひとつで味わう脳内体験に満たされずに、あえて未知の“荒野”へと自分の足で踏み出してみる。玉木が昨年2022に掲げた「自然と交わる」というテーマともつながってくるだろう。
玉木「しんやジジが来るまではもっと人間的な心の余裕がない感じだったよね。」
酒井「うん。」
玉木「去年動物さんが増えたことで…パッと空気が変わったね。」
酒井「うん。ほんと“潤滑油”みたいな、な。“クッション材”ってゆうかな。」
玉木「皆んなの“クッション材”として、しん・ジジの存在があって。仕事の合間に一緒に散歩に行ったりとか。」
—— 気持ちが切り替わる…。
玉木「自分の仕事をしん・ジジとの散歩の時間に冷静になって俯瞰出来るというか。皆んなで助け合ってあの子たちを育ててゆくという…それによって、皆んなの心がちょっと優しくなったってゆうのがあって。」
—— はい。
玉木「なんか社内の雰囲気・空気感が良くなったという。スタッフの子どもがよくここへ来るってゆうのもあるし、皆んなで子どもたちを育んでゆくみたいな。ミーティングしてても空気がギスギスしなくなった。お互い協力し合おうね、という風に変わりつつあって。良い兆しだと思うから、さらに深く語り合えるように今仕向けていってる…(笑)。」
—— 「まくチーム」にインタビューした時も、ヤギさん2匹が来て、気持ちが癒される、心が豊かになる、この子たちのためにも頑張れるとか、動物たちとの触れ合いを通して日々生きてることを実感している様子を感じたんですが、スタッフ皆さんにも波及している感じですか。
玉木「もちろん関心のない子もいるけど、全体的に何かしらの関わりがあるから。」
—— 動物たちをふと見かけるだけでも気持ちが違うでしょうしね。
玉木「うん。柵で囲って飼ってるわけじゃないから、どこまでが安全かの線引きとかも含めて、動物たちとのコミュニケーションが必要になってくるわけでしょう?それってすごい…五感を使うんですよ。」
—— なるほど…。どう対応するか、感性や判断が試されるところでもあるでしょうし。
玉木「見られてるし。相手もそれに対して対応してくるから。本能を鍛える、良い“実験”の場にはなってるのかなと観てる。」
—— はい。
玉木「今年は更に動物が増えることもあって、より五感を刺激されるスタッフが増えてゆけばいいと思う。やっぱり、ヴァーチャルの世界にどんどんどんどん引っ張られてゆく世の中だからこそ…映像の美しさとか『没入感』とか考えると、これは多分抗えない、これからの若者は皆んな流されていっちゃうだろうなと。」
—— 究極、周囲がどんなにリアルに悲惨な状況でも、夢のような仮想現実の世界に浸っていればシアワセ…というような方向に行ってしまうかも…。
玉木「可能性はある。そこはtamaki niimeとしてもけっこう議論してて、対策は要るよね、と。リアルを愉しまない人たちが圧倒的に増えちゃうとすると、服なんてどうでもよくなっちゃうかもしれないし。」
—— 確かに。画面の中で自分のアバターに着せ替えしてる方がいいとか。
玉木「で、自分たちはパジャマでいいとかね。…ありうるけど、でも、動物とともにある私たちの今の生活とヴァーチャルの世界に浸るのと、何が違うのかって言ったら、ヴァーチャルの場合、『五感を刺激する』っていう行為が削られていっちゃう。」
—— なるほどですね。
玉木「…ってことは、『人間性』がなくなる。人間の、動物である部分が損なわれるということは、人間としての豊かさが失われちゃうから。ヴァーチャル世界で目先の愉しさはあるかもしれないけど、人間が豊かにはならない。」
—— うぅ〜ん…。。
玉木「そう答えが出たから、ヴァーチャル志向の人たちにこそ、“入り口”としてでよいから、『niime村』を知ってもらって、リアルな世界へと引っ張り込む。五感を刺激することによって得られる感動をちゃんとリアルに体験してもらえるようにするために、人とのそんな関わり方の仕組みをつくっていこうというのは考えてます。」
なぜ動物だったのか。なぜ「niime村の創造」なのか。そのひとつの核心的な答えが、玉木の口から語られたように思う。
動物たちという、リアルな存在と日々向き合い、ひるがえって、私たち人間ってどうなんだろう?と己れに問いかける。
誕生から成長へ円熟へ死へと。そしてまた春を迎える、自然の法則に則した生命の営みの中で、人も動物も、子どもも大人も、日々新たな豊かな関係性を結ぶ、共生の村を創造してゆく…。
—— そこには“ヴァーチャル”に対して、という意識は特になかったのかもしれませんけど。
玉木「なかった。そこは。」
—— 結果的にそこへもつながっていたというか。
酒井「ある意味“放牧実験”やんな。人も動物も解き放ってさ、どうゆう行動をするのかってゆう。」
玉木「うん。フリーな“放牧”ですよ、この場所で。」
酒井「しんとかスゴイと思うのは、周りに皆んながいてもtabe roomのカウンターにポン、と飛び乗るのがクセなんですよ。そういうことをやって良いのかな?アカンのかな?なんて躊躇せずに出来てしまう。そこが必要なんですよ、これからは。」
—— ためらわずに。
酒井「動物なんだということを皆んな自分で自覚して、人の目を気にするとかじゃなくて。失敗か失敗じゃないかなんて、どうでもいいんスよ。そこまで突っ込めるかどうか。」
玉木「興味を持ったことに対して、人の目を気にせず突っ込んで行けるか。」
酒井「そうそう。」
玉木「スピードが勝負だから。そこで躊躇したら多分負ける。」
酒井「ほんとに『五感を研ぎ澄ます』とか『本能を呼び覚ます』ってのは、なにか危ういような状況の方が、ポンッ!と、なんか『火事場のクソ力』的に発現するから。」
—— 即座の反応として。
酒井「そう。逆にゆるいこと、『成功体験』からは本能的な感覚って呼び起こされないんですよ。もちろん人間的な歓びや幸せは得られますけど。」
玉木「成長するためにはね。」
—— リスクを負え、と。
酒井「皆んながそれぞれに、今から、これからの人生をサバイブする感覚で、生き残るんや、って気持ちを持つことが結論やと思いますよ。」
—— う〜ん…。。
酒井「その気持ちを持てれば、何やったってうまくいくというか、良い方向にしか転ばないと僕は思うから。そんな風に生きてる人こそが皆んなを幸せに出来るから。」
玉木「だから結果的には良かったよね。皆んなを“放牧”してみて。野に解き放って、何がやれるかやってみなさい、って言って。実際にやらせてみた。で、やれることも出来たし、良い動きもあった。」
—— はい。
玉木「ただ、いざって時や困難に直面した時に…私だったら、力織機入れて自分で織り始めるとか、ショール一本で行こうと決めて突っ走るとか、『タマスク』に振り切るとか、そうゆう“危機的状況”の時にダンッ!と何かやり出す、そんなスピード感だけは素早かったんですよ。これッ!って決めたら。」
—— そうですよね…。
玉木「こうと決めたら、次の日から振り切れる。多分それが、私たち2人にとってのビジネスの成功の秘訣だったから。そこがないんですよ、私たちが抜けると。なんとなく売り上げも上がるし、なんとなくは上手く行くんだけど、今がチャーーンスッ!!って時を逃しちゃうの。」
—— 勝負時のタイミングということでしょうか。
玉木「チャンスを逃さない。そこがオオカミ的・動物的な感性やし。」
—— 即、走り出すという。
玉木「で、動物を増やすと言ったらもう、今年は二十何頭に増えちゃうからね。」
酒井「うん。」
玉木「(酒井に)ワクワクでしかないな?(笑)さあどんな子が来るんだろう??」
酒井「これは絶対書いてほしいんですけど、“放牧”した結果、皆んなほぼほぼ“ポンコツ”やったんですよ。」
—— …。
酒井「でも、元を辿れば、生まれた時って皆んな“ポンコツ”なんですよ。なんもできないでしょう?おぎゃあ、と叫ぶしか。」
—— …ええ。
酒井「純粋だから。良い意味では、無茶苦茶何も知らないゼロの状態なんですよ。」
—— ピュアな。
酒井「一方から見れば、なんも役に立たない“ポンコツ”なんですよ。そういう意味では皆んなポンコツ。僕らももともとポンコツやから。自分たちが“ポンコツ”やと自覚することって絶対大事なんで。」
—— ああ〜…、なるほど!
酒井「ポンコツやからこそ、あ、こんな風に何かを取り込んでみようかな?とか、こうなろうかな?こうしてみようかな?とか。トライしてゆくことって、自分のことをポンコツやと思えてないと出来ないんですよ。」
—— なりふり構わず、必死に。そうですね、出来ないですね。
玉木「カッコつけちゃったら、ダメだよね。」
—— 自分の限界を痛いほど思い知って。
玉木「そうなの!」
酒井「そう!でないと、人に頭下げれないし。」
玉木「昨年は皆んなで限界を知った!」
酒井「ポンコツだって自覚したら、お願いします!、って人にも素直に言えるし。」
—— そうですね…。
酒井「そうゆう意味での、皆んな“ポンコツ”やったし、僕ら2人は元々ポンコツやったから。ちゃんとそこを自覚して、ポンコツなりに、どうやったらそのポンコツを…」
玉木「活かせるか!」
—— “ポンコツ”だからこそ、失うものはないんですよね。
酒井「ないんスよッ!」
玉木「そう!だから捨て身で行けるのよ。その気持ちにならないとダメでしょ。」
—— そうですよねぇ…。
酒井「うん。」
玉木「失うものは何もない、得るだけだッ!そう思えば強い。」
酒井「ほんと、“ポンコツの極意”ですよ。」
—— ほんまや…。それ、スゴイ、名言ですね。」
玉木「また名言出ちゃった!(笑)」
酒井「自分はスゴイと思い込んでしまってようが、いつまでも人間って“ポンコツ”やし。」
玉木「何事もやってみな、わからんしなぁ。」
—— “ポンコツ”ならではの“醍醐味”もある、みたいな?
酒井「そうそうそう!それですよ!!」
玉木「そうだよぉ〜。」
酒井「それこそがサバイブ、生きてるぞぉーーッ!!ってゆう実感やし。…そう。だから、人間、人生終わるまで“ポンコツ”で、どんなポンコツになれたかな〜ってゆうだけの話なんで。」
玉木「“ポンコツ”でいたいから、新しいことに挑戦するし。知らないことを知ってく愉しみやな。」
酒井「そう!それはポンコツやからこそ、出来る。」
玉木「もちろん読んだり見たりでも勉強できるけど、体験から学ぶってゆうところに、重きを置いてやってほしいな。」
—— 体験して学ぶ。そこには謙虚さも含まれますね。
玉木「うん。」
酒井「“ポンコツ”イコール謙虚やから。」
玉木「それ大事やね。」
酒井「うん。」
玉木「そうそう、…去年はまたひとつ夢が叶ったんやな?」
酒井「何?」
玉木「畑でコットンが大きく育ったから、集合写真撮ったんやな。」
酒井「ああ、撮った撮った!」
玉木「皆んなで、コットン採ったぞーーッ!!って。」
—— すごくよく育ってましたよね。
玉木「これまではずっとあまり大きくならなかったのが“菌ちゃんの土づくり”もあって。やっと、『まくチーム』とモノづくりのチームが交わって、皆んなでやろうってなったから。」
—— 「まくチーム」の皆さんも今、ほんと活き活きしてますよね。
玉木「ねっ、面白いよね。愉しみだね。」
酒井「結論。今年は『ポンコツの極意』です!」
玉木「そうですよ。」
酒井「『ポンコツの極意』をしっかり理解して、自分は“ポンコツ”やと自覚して、しっかりと学んで行こうね、ってゆう。」
玉木「そうゆう年にしましょう。」
—— 「ポンコツの極意」を各々自分の内に落とし込んで自走してゆくと。
酒井「そうです。」
玉木「ウチが自ら動き出す人を“大量生産”できたら…もう、繁栄しかないよね。」
—— 「一点モノ量産」から「一点ビト量産」へ(笑)。
玉木「ウチは『一点ビト量産主義』です!、って言える…でもほんとモノづくりは人づくりだと思うから。だって愉しいことだったら皆んな勝手にやるじゃないですか?」
—— やりますね。
酒井「うん。」
玉木「そこのスイッチさえ押すことが出来たら、もうどんな子がウチに来ても、なんでも出来るから。」
酒井「皆んなデコボコでも全然よくって、かえって色んな凸凹がそれぞれに自走してるのがおもしろい。」
玉木「ウチはデコボコになった時にベストな状態になる仕組みになってるからオモシロイ。ほら、『一点モノ量産主義』って、『ぜんぶちがってぜんぶいい。』だから。」
—— “ふぞろい”でいい、と。
玉木「え、こんなモノが?って言う人もいたとしても全然いい。そのかわり、これがイイ!って人が一人いてくれれば、それは正解。違う方がいいから。皆んな違ったやり方で、違う能力で、色んなことをやってくれる方が、最終的に多様性が出てくるから。」
—— なるほど…。やっぱり、すべてつながってきますね。
酒井「僕ずっと想ってたんやけど、僕らは『ファッション・ブランド』ではないんですよ。僕らは『ネイチャー・ブランド』やと。」
—— 「ネイチャー・ブランド」!
酒井「はい。ネイチャー=自然じゃないですか。僕らが表現するものは『すべて』やから。」
—— はい。
酒井「その中のコンテンツのひとつに服とか色んなものがあるとしても、僕たちが表現するのは『大自然』であり『地球』であり。僕らはその一部やから。すべてをこれから表現してゆく。」
—— まさに“whole earth”=「地球全体」というか。
酒井「はい。『ネイチャー・ブランド』ということをスタッフに提言したんですよね。プラス、さっき言った『ポンコツの極意』ですよ。そのふたつさえ自覚すれば、絶対走れる。」
玉木「…また描いといてな!」
酒井「『ポンコツの極意』な。」
—— 「常識を疑え。」に続いて。
玉木「Labの床に。皆んなに摺り込む(笑)。」
書き人越川誠司
< continued from the part 1 >
Sakai: So I think ‘Watch and Learn’ back in time is an excellent method ….
—— Yeah.
Sakai: Nowadays, you expect to be taught from beginning to end, but when I started working at 17 years old, I was scolded if I asked questions. I wondered how I could know such senses and how far I could get them.
—— I see.
Sakai: Watching and learning techniques by sight, I expressed myself before them and got praised or evaluated.
—— You gained sense and gained know-how naturally.
Sakai: You are exactly right.
—— You learn by doing.
Sakai: Yes.
Tamaki: Yeah.
—— During my training time in graphic design, I watched my teacher’s movements and moved my hands. I learned it physically.
Sakai: Now our staff can join the company without a training period and can start designing soon after being hired.
—— They should be thankful for that.
Sakai: Since the development of the computer system, it’s easy to develop specific patterns. It’s easy to classify people. Even though diversity is worth respecting, there was more variety back in time.
—— More types of people could not fit into specific categories or write them in the data.
Sakai: On the contrary, the diversity of computerised techniques made the ways people simplify.
—— It’s too poor to be controlled by information. So, for example, when you work with your hands, you realise how important they are.
We live in a world where virtual things threaten us. You dare step into the unknown world without being satisfied by the computer experiences given by clicking the screen. It will connect with the theme, ‘Communication with nature’, Ms Tamaki announced in 2022.
Tamaki: Before Shin and Jiji came, we needed more space to care about other stuff.
Sakai: Indeed.
Tamaki: Things changed since we got more animals last year.
Sakai: Yeah, they are like the oil that makes machines run smoothly or like cushions for us.
Tamaki: Shin and Jiji have become everyone’s emotional support. We take them for a walk at work breaks.
—— Your feelings can change.
Tamaki: While walking with Shin and Jiji, we can observe ourselves and think about our work calmly. Helping and caring for them together, we have become more kind.
—— I see.
Tamaki: The company’s atmosphere has improved, and the staff’s children come here often…looks like they are caring for children together. Discussion in our meetings became more accessible. It’s getting to change our attitude that we want to cooperate. It’s a good sign, so we are trying now to be able to talk deeply. (laugh)
—— When I had an interview with the ‘Maku team’, I felt they were healed and enriched their hearts with two goats, even being encouraged to work for them. I strongly felt they were living happily through interacting with animals, though. Is it happening to all of your staff?
Tamaki: Of course, some staff are not interested in them, but we all had some involvement with them overall.
—— You may feel different even just seeing animals.
Tamaki: Yeah, since they are not kept in the fence, we need to communicate with animals, including considering safety. That’s where we need our five senses.
—— I see. You are challenged to use your senses and judge how to cope.
Tamaki: We are observed by animals, and they respond to us. This may be a chance to train our instincts and have a good experience.
—— I see.
Tamaki: Increasing the number of animals this year; I hope more staff stimulate their senses. We live in an age where the virtual world attracts us. Moreover, though…thinking of the beauty of screens and their immersion, you wouldn’t win, and young people all drift into there.
—— After all, even though how terrible their real situations may be, they make themself stay happy by dreaming in unrealistic world.
Tamaki: It’s possible. In ‘tamaki niime’, we often discuss it and realise we need to help them. If more people don’t enjoy reality, they don’t care what they wear.
—— That may be true. They may enjoy changing their avatar’s clothes on the screen.
Tamaki: On the other hand, they are all right, just wearing PJs, which can be possible. What’s the difference between being in the world now and a virtual world? In immersion in the virtual world, you don’t have much chance to stimulate your five senses.
—— I see.
Tamaki: That means you will lose humanity. Lacking a part of an animal’s elements means losing richness as a human being. In the virtual world, you may have fun temporarily, but you don’t develop rich senses of humanity.
—— Oh, I see.
Tamaki: I want people who like the virtual world to know ‘niime village’ as their entrance to the real world. I am thinking of systems of interacting with people to get a profoundly emotional experience by stimulating their five senses.
What do you have to do with animals? Why is it the ‘creation of the niime village’? One of the questions was answered from the mouth of Ms Tamaki.
Interacting with animals daily, which is a very realistic existence, you question what we humans are.
We experience from birth to growth and fulfilment till death, we have a new spring again. In the course of life, which is the natural law, children and adults, all create a village of living together that ties rich relationships daily.
—— You didn’t have intentions of a ‘virtual world’ precisely, right?
Tamaki: No, I didn’t.
—— It was just connected as a result.
Sakai: It’s like a ‘grazing experience’ for releasing animals and humans and watching how they react.
Tamaki: Yeah, it’s a free ‘grazing’ here.
Sakai: I was impressed that Shin has a habit of getting on a counter of ‘tabe room’ even though everyone is there. He does it without hesitation, not thinking about if it’s good to do or not. That’s what we need to do from now on.
—— Without hesitating.
Sakai: You need to realise that you are an animal without caring about other people. It doesn’t matter if it’s a failure, but it matters if you could try it with all your might.
Tamaki: The matter is if you could try your best without caring about others for the things you are interested in.
Sakai: That’s right.
Tamaki: It matters how fast you start acting. If you hesitate, you probably can’t win.
Sakai: ‘Boost sensitivity’ or ‘recall your instincts’ would work in emergencies like ‘superhuman strength’, a Japanese idiom.
—— As a quick response.
Sakai: Right. Reversely, ‘success experiences’ which slowly happen, don’t get your instinct senses. Of course, you can bring happiness or joy, though.
Tamaki: For your growth…
—— You have to take a risk.
Sakai: The bottom line is if you want to survive for your future, each one has to work for it with firm determination.
—— I see.
Sakai: If you could determine that, everything would go well, or nothing would go in the wrong direction. The people living with such a will could make everyone happy. That’s how I understand it.
Tamaki: So, as a result, it was good to make everyone accessible. I told them to try and see what they could do. I let them do it, and they did what they wanted to do and achieved good results.
I see.
Tamaki: In case of emergency, when I faced risky conditions, I quickly made up my mind, such as deciding to work with power looms by myself, focusing only on shawls, or limiting myself to selling ‘Tamask’ once I determined to.
—— That’s right.
Tamaki: Once I decided to take it this way, I worked on the details the next day. That must’ve been the secret of our business for the two of us. If we leave the company, the sales go up gradually, and the business does well somehow, but they miss the best chance on business.
—— The best time to win the game?
Tamaki: You can take the chance; you need the instinct of animals or wolves.
—— You need to dash.
Tamaki: Yeah, talking about increasing animals, we will have more than 20 animals this year.
Sakai: Yeah.
Tamaki: (to Sakai) We are so excited. What kinds are coming?
Sakai: Could you write this one? As a result of letting them be accessible, I found that most are ‘spoiled’.
—— …
Sakai: Thinking about our original ourselves, we are all ‘airheads’ when we were born. We can’t do anything besides cry.
—— You are right.
Sakai: We are very pure. In a good way, we are zero, knowing nothing.
—— Very pure.
Sakai: From another side, we are ‘spoiled’. In that sense, we are original ‘airheads’, so recognising that is important.
—— Oh, I see.
Sakai: Knowing we are ‘airheads’, we can try here and there. We can’t do it if we don’t know what we are.
—— We work desperately. Well, we can’t do it.
Tamaki: Don’t try to look cool.
—— You need to know your limitations.
Tamaki: You are right!
Sakai: If you don’t know, you can’t be humble.
Tamaki: Last year, we all learned our limitations!
Sakai: If you know you are ‘nothing’, you can be humble and ask people.
—— You are exactly right.…
Sakai: In such meanings, we are all ‘nothing’, and we both are initially ‘airheads’. Realising yourself as being an ‘airhead’, how do you…
Tamaki: How do you make your ‘airheads’ use it?
—— Being ‘airheads’, there’s nothing to lose.
Sakai: No, nothing to lose.
Tamaki: Right. So you can do anything with your life. So it would be best if you did it with that spirit.
—— I see.
Sakai: Yeah.
Tamaki: There’s nothing to lose. You can only gain! You can be strong if you think so.
Sakai: Absolutely. That’s ‘The Secret of Airheads’.
—— That’s right. Wow, that’s a great quote!
Tamaki: I made a great quote again! (laugh)
Sakai: Even though you believe you are great, you are an airhead.
Tamaki: You only know what you can do once you try.
—— There’s a perfect sense of taste that only ‘airheads’ can create.
Sakai: You said it! That’s it!
Tamaki: That’s right.
Sakai: That’s the natural feeling when you are surviving. You will be an ‘airhead’ until the end of your life. It’s just a matter of how much you could do as an ‘airhead’.
Tamaki: I challenge new things because I want to stay an airhead. It’s fun to get to know new things.
Sakai: Yes! You can try because you are an ‘airhead’.
Tamaki: We want to focus on learning from our experiences, even though we can study by reading or watching.
—— You need to be humble when you learn from experiences.
Tamaki: Yeah.
Sakai: Being ‘airheads’ equals being humble.
Tamaki: That’s essential.
Sakai: Yeah.
Tamaki: Well, one of our dreams came true last year.
Sakai: What was it?
Tamaki: We took a group picture in the field last year because our cotton bushes grew. Remember?
Sakai: Yeah, we did. We did.
Tamaki: Yeah, we were so excited that we could pick cotton.
—— They grew big.
Tamaki: They didn’t grow well until now, but they began to grow well with the help of ‘Kinchan’s bacteria’. ‘Maku team’ and the ‘Creation team’ guided everyone to do that project.
—— The ‘Maku team’ are so happy and working lively now.
Tamaki: Yeah, it’s so fun and exciting.
Sakai: The conclusion! ‘The secret of airheads’ is this year’s goal.
Tamaki: That’s right.
Sakai: Understanding ‘the secret of airheads’ well, realising that you are the one, and learning it.
Tamaki: Let’s do it this year.
—— Incorporating ‘the secret of airheads’ into yourself and learning.
Sakai: You are right.
Tamaki: If we can get the ‘mass production’ of workers who work with the concept on your own, there’s nothing but prospering.
—— It’s like ‘one item production’ to ‘one person production’. (laugh)
Tamaki: Our company has a principle of ‘One Person Production’. Creating things means creating people because people make things without being asked. After all, those are fun things to do.
—— Yes, they are.
Sakai: Yeah.
Tamaki: If you understand that concept, anyone who joins our company can do anything.
Sakai: It’s okay if they have trouble or weaknesses. It’s even enjoyable to make it happen that each original creative produces uniqueness.
Tamaki: Interestingly, we get the best creations where there are difficulties. See, our concept of ‘one item production’ means ‘each difference, each great.’
—— It’s okay to be irregular.
Tamaki: It is all right if a person doesn’t accept our product, but it is right if there’s someone who loves that same product. The difference is worth it. People with different ways and skills and various works produce diversity.
—— I see. So everything is connected.
Sakai: I have thought that we are not a ‘fashion brand’. We are a ‘nature brand’.
—— You are a ‘nature brand’!
Sakai: Yes, we are. What we express is all about nature.
—— Yes.
Sakai: Our products, clothes, and other things are parts of nature or earth of what we want to express. Since we are parts of it, we will try to describe them all.
—— You want to express ‘whole earth’.
Sakai: I announced to our staff that we are a ‘nature brand’, and mentioned ‘The Secret of Airheads’ as I explained previously. You can dash for your best if you can understand these two concepts.
Tamaki: Write it!
Sakai: I will write ‘The Secret of Airheads’.
—— I will write it following ‘doubt your common sense’.
Tamaki: I will do it on the Lab floor, imprinting it on everyone’s hearts. (laugh)
Original Japanese text by Seiji Koshikawa.
English translation by Adam & Michiko Whipple.